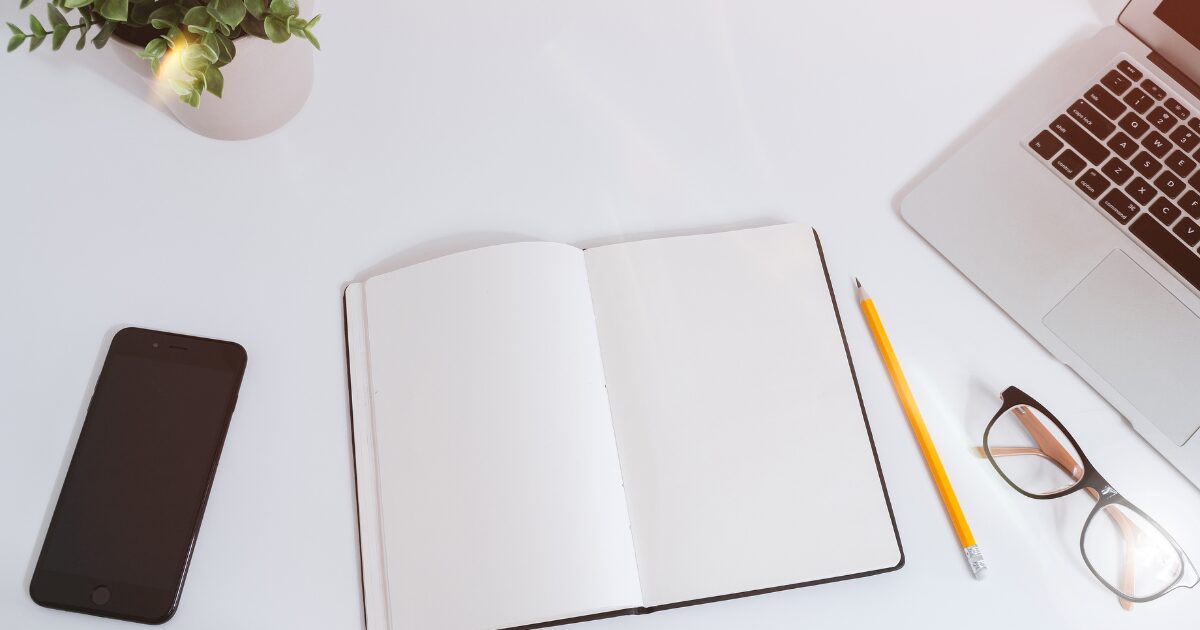👉1.最初に整えたい“心構え”
精神保健福祉士の試験は、知識の量と理解の深さ、そして長期戦を乗り越える持久力が求められます。仕事との両立を目指すなら、いきなり気合で突っ走るよりも「習慣化」「仕組み化」を確実に身につけることが必須です。
“全部はできない”前提で計画を立てる
完璧を求めすぎないこと。意気揚々としているときには、立派な計画を立てがちです。仕事を持っている人は、自分の可能性の6割くらいで予定を立てるとよいでしょう。毎日30分でも「続ける」ことが大切です。遅々とする日があっても、継続できる自分に誇りを持ちましょう。
「できなかった日」を責めないこと
体調不良や、生活のリズムが乱れることもあります。柔軟に立て直せる気持ちの余裕を持ちましょう。うしろ向きの時間程無駄なものはありません。
「学ぶ理由」を言葉にしておく
迷いや不安に負けそうなとき、自分の原点が支えになります。
毎日の多忙に流されないように、ブレない自分の気持ちを確認し、文字化しておくといいですよ。
👉2.勉強を始める前に準備するもの
勉強道具を揃えることは、気持ちのスイッチを入れる一つの大事な儀式でもあります。
スケジュール帳(紙 or アプリ)
長期戦だからこそ、可視化できるツールがあると便利です。また、使いこなした予定表は、今後の大切な道しるべになるものです。
過去問題集(直近3年分ほど)
最初は問題を解かなくてもOK。出題傾向を“眺めて”おくだけで、全体像をつかみましょう。
この「眺める」時間は、気持ちを整えて、目標に向かう決意を固めてくれる大事な時間です。
テキスト類(基本書+まとめ本)
本格的な勉強はここからです。まずは一冊の中身をざっくり把握して「自分に合いそうかどうか」確かめてみましょう。参考書類にも不思議と相性があるものです。
そのかわり、コレと決めたら少々とっつきが悪くとも、最後まで付き合うことで自分のものにできるものです。
勉強グッズ
静かな時間を作れるイヤホンや、仕事の休憩中に見る単語帳グッズなどはおすすめです。
また、仕事の疲れを気にせず、自分の勉強時間の効率を図るには、リラックスできる環境を整えることがとても大切です。
👉3.試験本番までの“ざっくり計画”
詳細なスケジュールは後から立てるとして、今の時点での「年間イメージ」があると安心です。
- 春(4月〜6月):準備・全体の把握期
→教材を選ぶ、生活リズムを整える、勉強時間の確保(必ず机に向かう習慣)に慣れる - 夏(7月〜9月):基礎学習・苦手発見期
→各科目の要点を押さえる、アウトプットも少しずつ開始しましょう。 - 秋(10月〜11月):応用・過去問演習期
→本格的に問題を解きながら実戦力をアップする時期です。 - 冬(12月〜1月):総復習・追い込み期
→弱点補強、模試や予想問題で調整します。
🌟おわりに
“何をすべきか”よりも“どうやって続けるか”を大事にする。
国家試験への道のりは、勉強そのもの以上に、自分の心と時間をどう扱うかが問われる旅です。
焦らず、慌てず、まずはペース作りから。
来年の春、合格通知を手にした自分を想像して、小さな一歩から始めてみましょう。